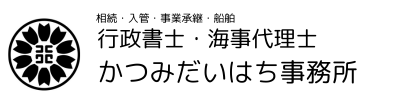当事務所が行う業務の特長
外国人雇用に必要な準備から提案します
少子高齢化、生産年齢人口の減少により、今後ますます外国人の雇用が必要になってきます。その担当業務やポジションも広がりをみせ、現場の担当者だけでなく、管理職ひいては経営職にまで、その活躍の場面は拡がってきます。他方で会社としては、従来の日本人中心の雇用形態や事業形態を変化させる必要があります。長く定着した雇用文化を変えることは、組織の形態を変えるのと同じくらい大きな変化となります。そのため、当事務所では、外国人雇用への備えの部分からご提案・アドバイスをさせていただきます。
はじめての外国人雇用
外国人雇用について、その適正化やあり方について様々議論されています。政府の方針や外国人雇用に関する制度・政策についても見直しが検討されています。人手不足対策としてあるいは技能の承継、事業の成長や海外展開等を検討する際に、まずは知っておくべき基本について、今後まとめ記事を掲載していきます。是非このページをブックマークしてください
特定技能制度から見る、外国人雇用
(1) 多くの就労系在留資格
在留資格というのは、日本に入国後に行うことのできる活動とその期間を定めた法的な資格で、法務省出入国在留管理庁のホームページに詳細な規定類が開示されています。その中で就労という活動が可能な資格が、就労系在留資格(就労資格)として19種類定められています。法務省出入国在留管理庁の就労資格に関するホームページ。19個もあると、項目を見るだけでも大変な労力が必要です。ざっくりつかむためにはどうすればよいでしょう。
ここでは、2019年に人手不足対応を目的に新設された、「特定技能」という在留資格を例にとって、その概要を知る事から始めることにしましょう。
(2)特定技能とは?
人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人を「即戦力」として受け入れるために法務省が創設した在留資格制度です。 技能実習制度が「技能習得と国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「労働力確保」を目的としています。
その目的は以下の二つに集約できます
(1)深刻な人手不足に対応するため、外国人材を労働者として受け入れる。
(2)技能実習制度とは異なり、帰国前提ではなく日本国内での就労を目的とする
その内容は2種類(1号及び2号)あります
(1)特定技能1号は、16個の事業分野で認められており、在留期間は通算で5年まで。技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。約35万人が在留中。
(2)特定技能2号は、1号の上位資格で、11業種に認められ、各分野に熟練した労働者に認められます。在留資格の更新回数の制限が無く、家族の帯同も認められる場合があるなど、優遇されています。現在約4千人が在留中。
(3)事業分野とは?
では、特定技能が対象とする事業分野とはどのようなものか。技能実習1号が対象とする16業種について見てみましょう。
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業